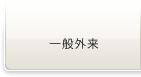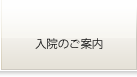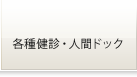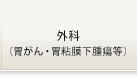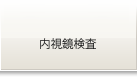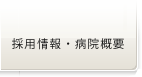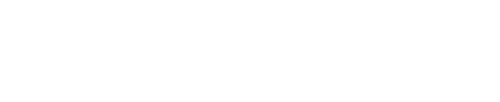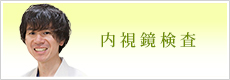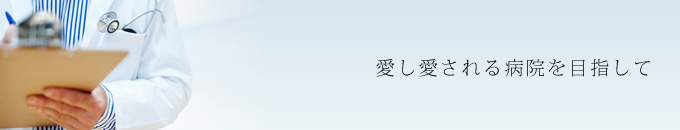
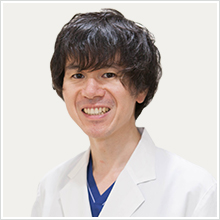
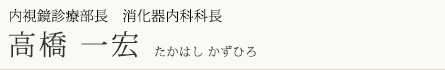
自己紹介
父と同じ有機化学の分野への進学を目指しておりましたが、ウィルス性脳髄膜炎、急性血小板減少性紫斑病で高校2年4月に入院し脳神経外科、血液内科で二人の先生と関わり、魅了され医師を志す契機となりました。
前任地の北海道では消化管早期癌の低侵襲内視鏡治療(ESD)を専門としながら内科・消化器内科診療を行ってきましたが、専門分野を絞って診療したい思いが強く、平成30年4月より関東へ勤務地を移しました。
患者さんへのメッセージ
2019年4月よりメディカルトピア草加病院へ勤務し4年経過しました。
当院消化器内科を受診いただく上でメリットとしてお伝えしたいことは「お腹の中の見える化」が可能になる点にあります。
消化器内科では下記の点に強みがあります。
・X線技師の協力により診察当日の腹部CT臨時撮影枠が多数確保されている
・超音波エコー技師の異常検出力、描出力が非常に優れている
・内視鏡室スタッフが人数、専門性ともに充実しておりケアがとても手厚い
・早期食道癌、早期胃癌、早期大腸癌については当院のみで治療完結が可能
・早めの内視鏡検査日程調節が可能で、診断から治療までの期間が短い
・外来診療は常勤医(各々週3回)のみで構成しており、一貫した診断、治療提供が可能
・外科との連携がスムーズで早期治療に結び付けられる(特に消化管粘膜下腫瘍)
消化器症状(胃の痛み、嘔気、腹部違和感、下痢、便秘など)は炎症性・腫瘍性病変のみならず、ストレス、自律神経の乱れ、ホルモンバランスの崩れなど多岐の原因により症状が出現します。診断を進める上では炎症性・腫瘍性病変の否定をすることから始まります。
受診当日に、否定できる疾患は否定すべきと考えており、上記の点から診断・治療開始が早くなる面にメリットがあると思います。
可能な限り、検査当日に結果説明させていただきます。挿絵を用い、帰宅後も検査結果を読み返すことで不安を解消できるよう努めております。
時々出現する症状でもかまいません。問診、診察のみならず画像診断も駆使し、お腹の中の臓器の見える化、そして症状の原因の理解を一緒に深めましょう。
咽喉頭異常感症や機能性胃腸症、過敏性腸症候群など症状の原因を画像でとらえにくい疾患に関しても、各種薬剤の変更、漢方薬も含めた多岐の治療をご提案させていただきながら粘り強く治療を進めていきましょう。
専門分野
消化管内視鏡診断、内視鏡治療、腹部画像診断
資格・認定医
日本内科学会認定医
総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医
日本消化管学会胃腸科専門医・指導医
がん治療認定医
ピロリ菌感染症認定医
日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化管学会胃腸科指導医
ヘリコバクター学会H.pylory感染症認定医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
出身大学・卒業年
| 平成17年 | 旭川医科大学 卒業 |
|---|
経歴
| 平成17年 | NTT東日本札幌病院初期研修 |
|---|---|
| 平成19年 | 同院後期研修 |
| 平成20年 | 市立稚内病院 内科医員 |
| 平成23年 | 苫小牧市立病院 消化器内科医員 |
| 平成24年 | 釧路労災病院 内科副部長 |
| 平成30年 | 練馬光が丘病院 消化器内科医員 |
| 平成31年 | メディカルトピア草加病院 |