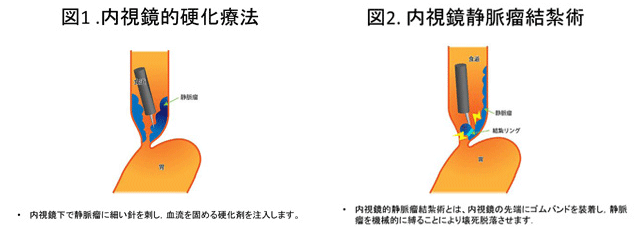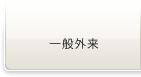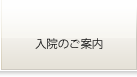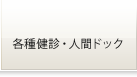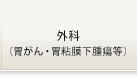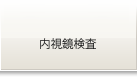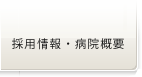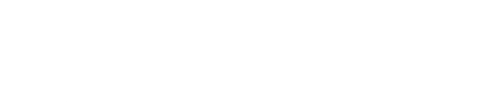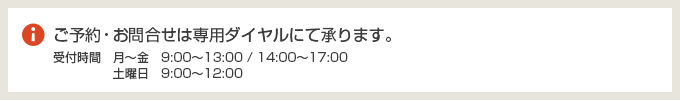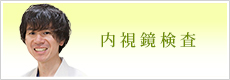食道の粘膜を流れる静脈が瘤(こぶ)のようにふくらんで曲がりくねってでこぼこになった状態をいいます。
胃にもできることがあり,その場合は胃静脈瘤といいます。
食道・胃静脈瘤の約9割が肝臓の病気である肝硬変が原因で出現します。
肝臓がB型肝炎、C型肝炎、アルコール性肝炎などが原因で慢性肝炎→肝硬変と病態が悪化していくと、肝臓が硬く凸凹になっていきます。そうなると肝臓にもどる門脈という血流がうっ滞するために門脈の圧が上昇し、血液は別の流れ道を探すことになり、側副血行路が作られます。その代表が食道・胃静脈瘤です。
静脈瘤が大きくなっても,たべものが通りにくいなどの症状はあまりありません。しかし食道の下部、胃の上部にある静脈が数珠のように大きく腫れ、時に破れて大出血を起こすことがあります。静脈瘤はおおきくなればなるほど出血する可能性が高くなり、一度破裂して大出血をおこすとショックになり、それにひきつづいて肝不全も併発し到死的な状況になることがあります。
今後破裂する可能性が高い静脈瘤に関してはあらかじめ静脈瘤をつぶす治療を行うことが、非常に重要になってきます。治療法には大きく分けて2種類の方法があります。内視鏡的硬化療法(図1)とは、内視鏡下で静脈瘤に細い針を刺し,血流を固める硬化剤を注入します。内視鏡的静脈瘤結紮術(図2)とは、内視鏡の先端にゴムバンドを装着し,静脈瘤を機械的に縛ることにより壊死脱落させます。この治療法の選択は病状や出血の状況を見て判断することになります。診断は内視鏡治療が必須なので、慢性肝炎や肝硬変を指摘されたことがある方で上部消化管内視鏡の検査をしばらくやっていない方は検査を行うことを勧めます。