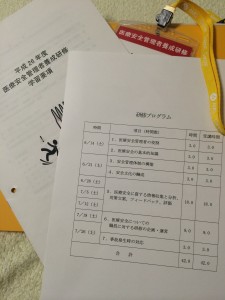こんにちは、放射線技術科の佐藤と申します。
僕は少年野球のコーチをしています。下は小学校1年生から上は6年生まで、約30名の部員がいます。勝ったり負けたりで、最近は少し勝てるようになって来ました。この間、すごく小さい大会ですが、準優勝する事が出来ました。その試合では有りませんが、印象に残った試合を紹介します。
チームの名前は藤心ジャガーズ。当時のジャガーズはあまり強くなく、弱小チームでした。対する相手(以下:Bチーム)はそこそこ強くて、ジャガーズが勝てる自信はほとんど有りませんでした。Bチームの特徴は、言葉が悪いのですが、汚い試合をします。相手チームにヤジを飛ばすのです。
「相手のピッチャーしょぼいよ!」「ストライク入らないよ!」「バッター打てないよ!」などバンバン言ってきます。ジャガーズのコーチや父兄はもう頭に血が上っています。Bチームの戦略にまんまとはまってしまいました。ジャガーズの子供達も頭に来ていますが、決して言い返しません。それは鬼より怖い監督から、ヤジは禁止されているからです。
その代わりにジャガーズでは仲間を誉め、激励します。例えば、自分のチームのピッチャーが三振を取ると「バッターしょぼいよ」とは言わないで、「ナイスピッチング!」「今のボールいいねぇ!」、相手チームがエラーしても「ナイスバッティング!」「足早いねぇ!」など相手をけなさないで、味方を誉めます。「ほめる野球VSヤジ野球」の対決が始まりました。
ジャガーズは弱いけど伸び伸びと、Bチームは強いけどガチガチ。と言うのもBチームは仲間にも、エラーをすると貶します。Bチームはエラーしない様にするため、動きが悪くなっていました。試合内容はファーボールが多いし、エラーも多い、まさに泥試合になりました。
結果は8対7でジャガーズの勝ち。僕は「あんな汚い野球をやるから負けるんだ。」「ざまーみろ!」と思い、勝ったにも関わらず、あんまり良い気分ではありませんでした。その時、ジャガーズの一人の6年生が来て、
「コーチ。相手のチームは野球が楽しくなさそうで、かわいそうだ。」と言いました。この子は相手がかわいそうと思えるんだ。僕は「ざまーみろ!」と思った気持ちを恥じました。恐るべし6年生!!そして僕は聞きました。
「ジャガーズは楽しいか?」
「うん。楽しい!!」
僕はめちゃくちゃその子を誉めてあげました。そして初めてこの試合に勝って良かった、この子達の、ジャガーズの野球が勝って良かったと感じました。そして、相手チームも楽しい野球が出来ればいいなぁと思えました。
子供達は素直です。叱られると泣くしいじける、悔しくても泣く。バカにされれば、けんかもする。そして誉められたり、激励されるとすごく頑張る。僕は十分に大人だし、十分におっさんです。それでも小学生の子供達から教わることが多々有ります。がんばる姿を見ていると頭が下がります。恐るべし小学生!!